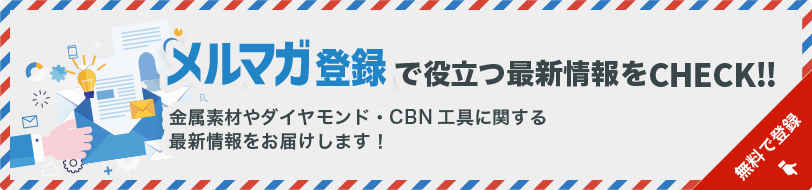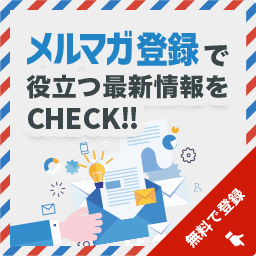夜、煌煌と明かりを照らして魚を取っている漁船を見かけたことがありますか。この灯りのことを集魚灯といいます。今回は、この集魚灯についてお話させていただきます。
1.集魚灯とは?
この灯りに昔は、篝火、石油ランプ、アセチレン灯などが使用されてきました。現在では、電気による集魚灯が広く活用されています。
2.集魚灯の種類について
集魚灯の種類について
集魚灯には、大きく分けて2種類の形があります。一つは、水上等灯(船の上にランプがある)=写真はイカ釣り漁船です。もう一つは、水中にランプを沈めて集魚する水中灯です。
漁をする魚の特徴によって分けているようです。
水中灯の中には200mの深海まで使用可能なものがあって、鯵・鯖・鰯・鰹等の青物の魚を取るのに使用されているようです。
また、ランプの中の種類として、フィラメントランプ・LED・放電灯の3種類があり、LEDが拡大する中でも昔から使われているフィラメントランプでしか取れない魚があったり、遠洋漁業に出たときは交換ランプがたくさん持っていくのでLEDだと高価なのでフォラメントランプを使用されている漁師さんもいるようです。
3.タングステンの役割
フィラメントのランプではタングステンワイヤーでフィラメントが作られていますのでその素材として使用されており、LEDランプはLEDの素子のなかにサファイアが あるのですが、サファイアを作るための容器としてモリブデン坩堝が使用されています。
放電灯ではタングステンの電極が使用されております。
それぞれのランプに対して、当社の製品が何らかの形で貢献しています"

4.まとめ
集魚灯のお話はいかがでしたか。タングステンフィラメントや、サファイヤ製造用の坩堝など、表には出てきませんが、さまざまなところで当社製品は活躍しています。日本人は最近、魚を食べなくなったといわれていますが、健康食品としても見直されつつあります。また、これからは秋刀魚の美味しい季節です。皆さんもこれから秋刀魚を食べられるときに今回のお話を少しでも思い出していただければ幸いです。(記:中野)